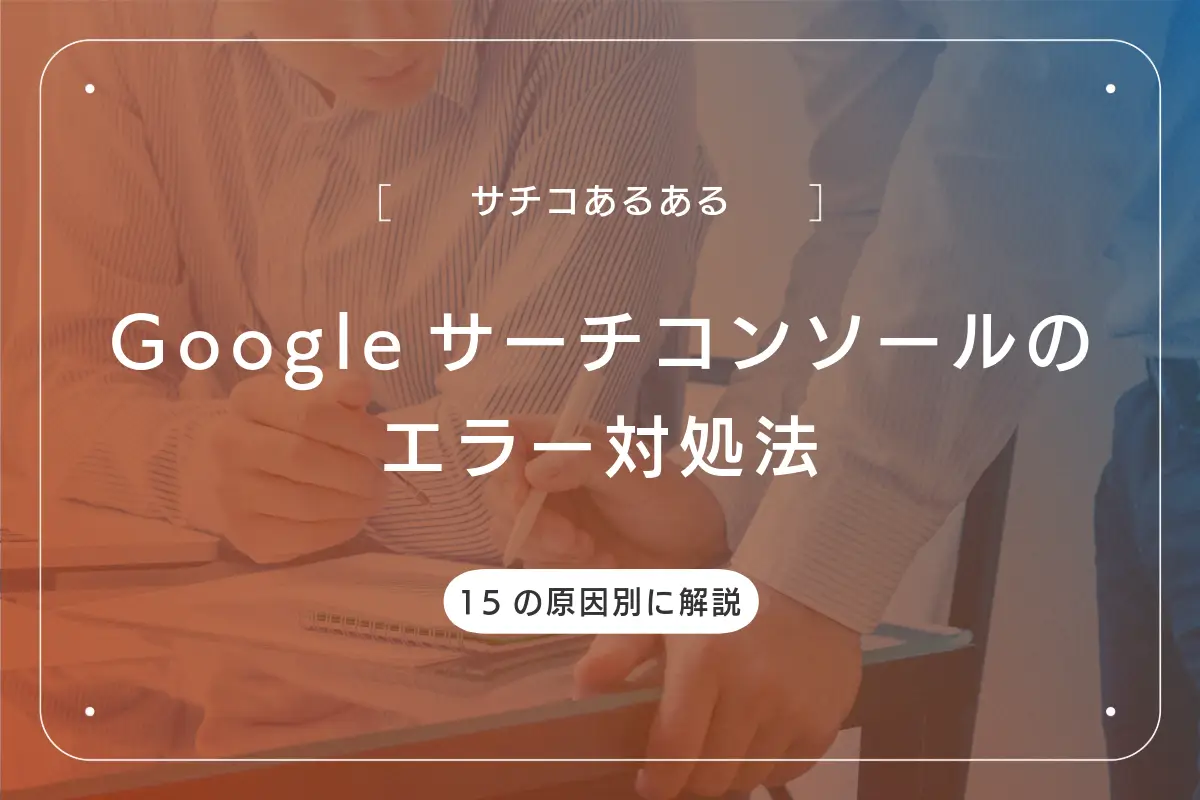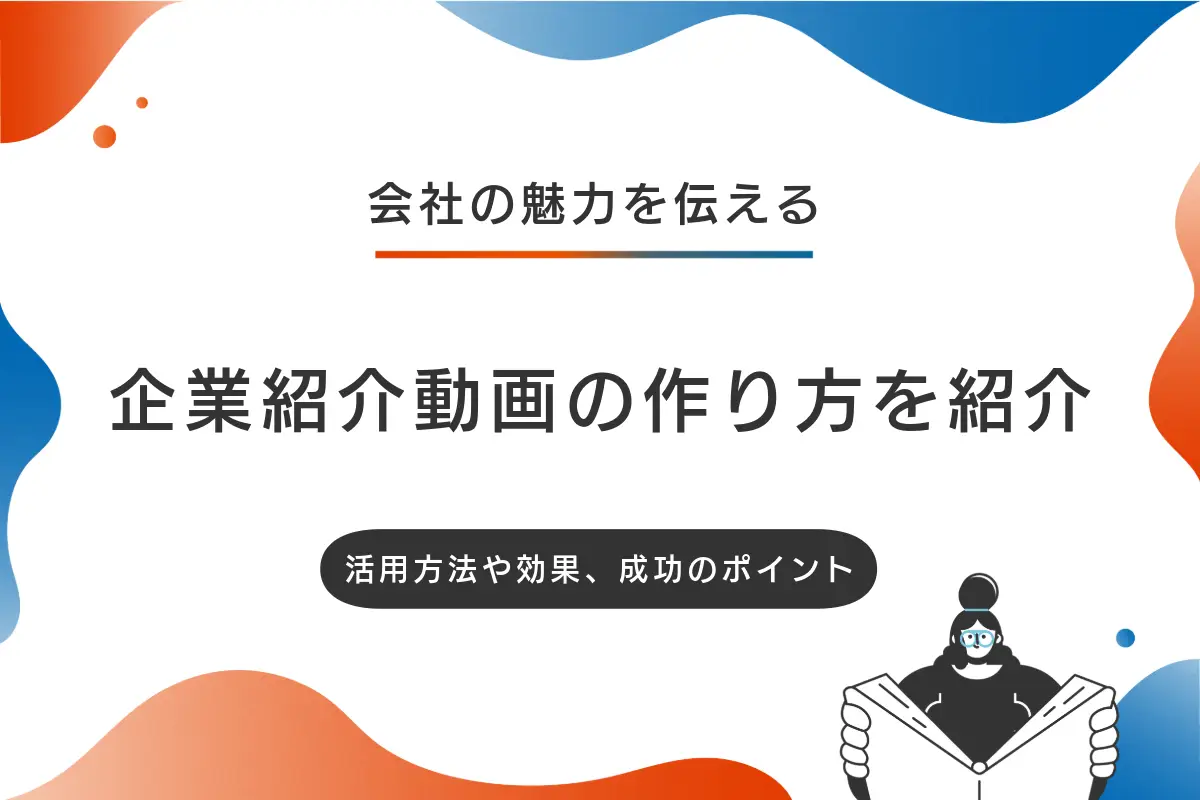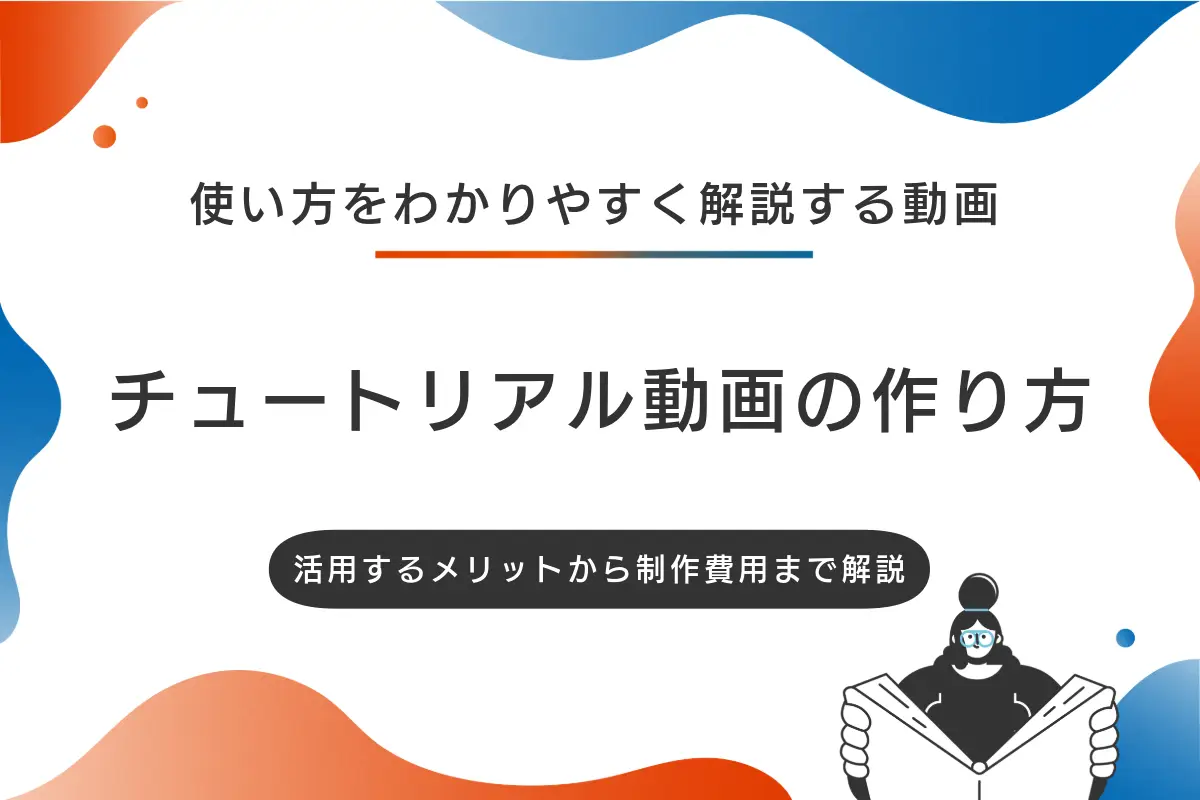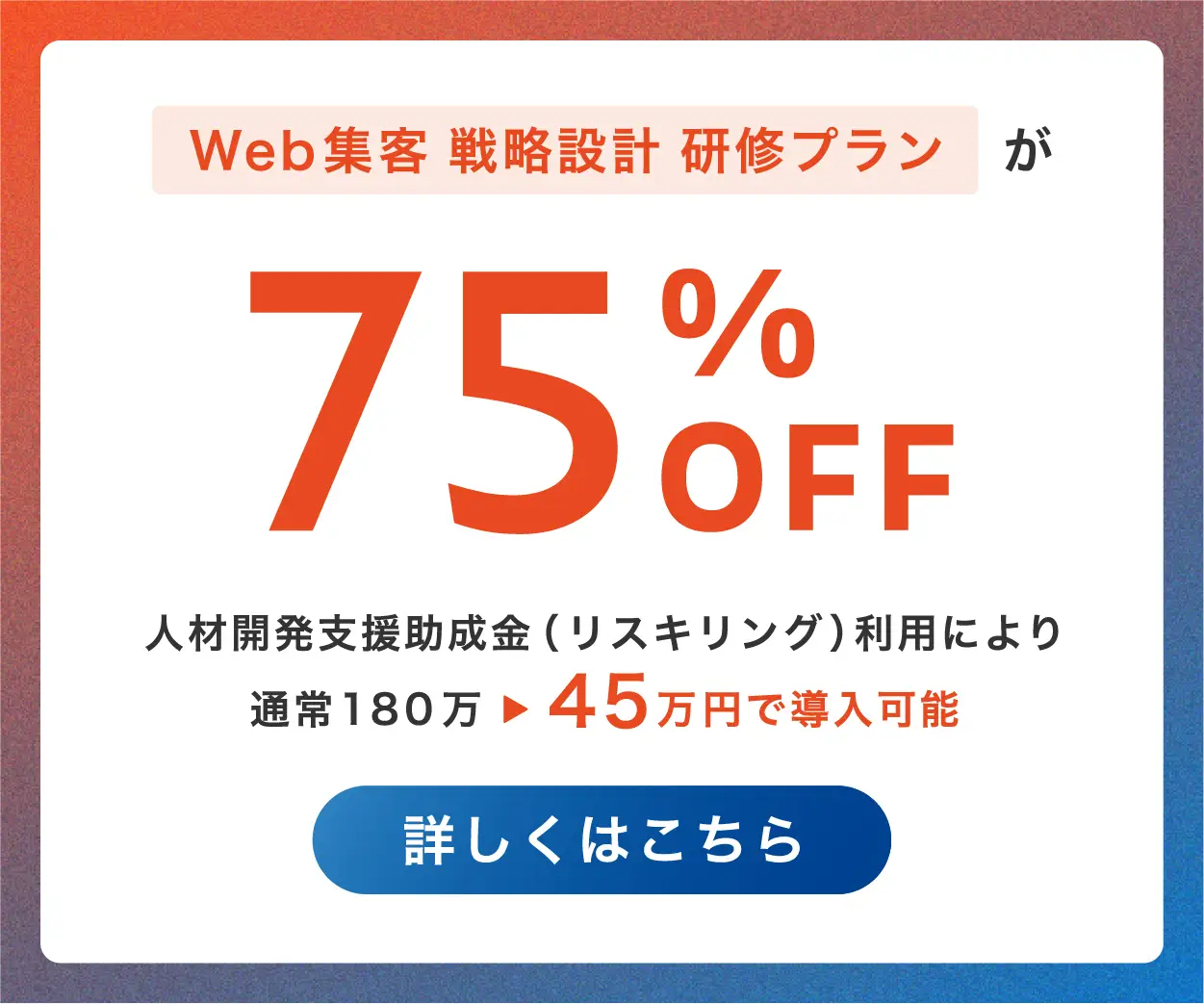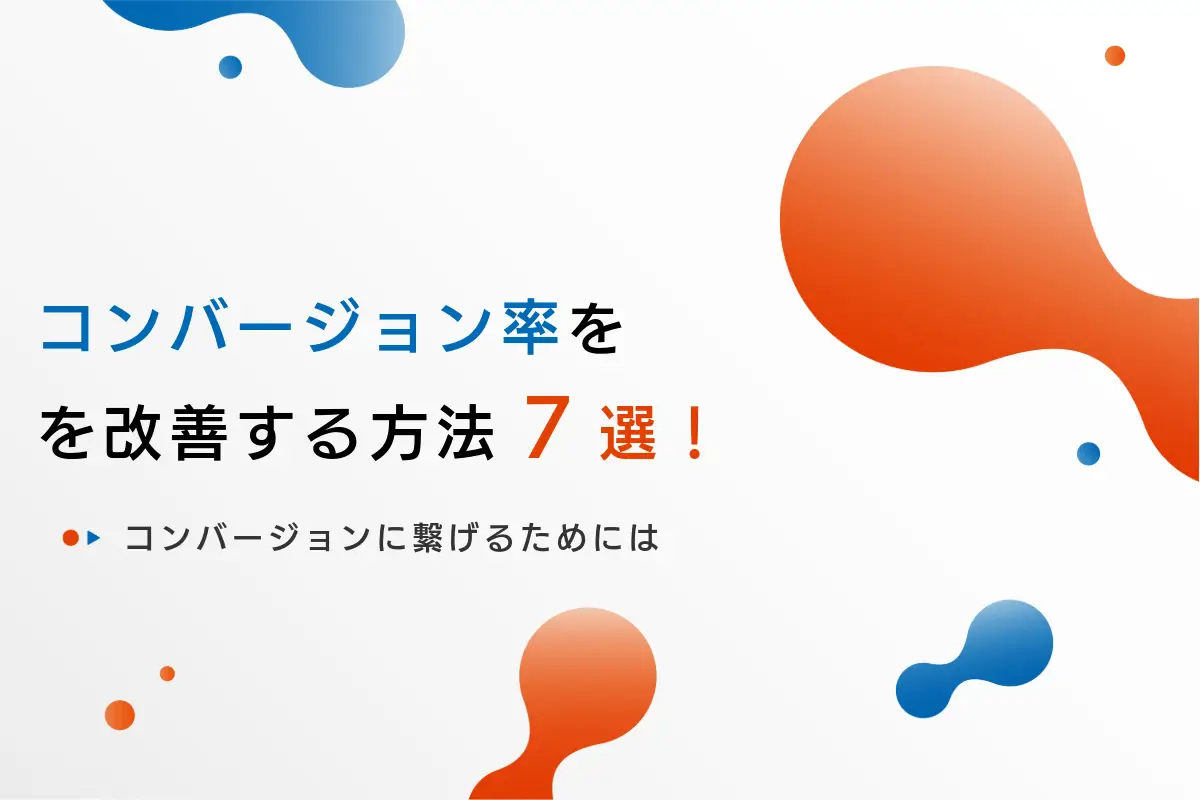
展示会用の動画とは?効果や費用、制作・活用を成功させるポイントを紹介
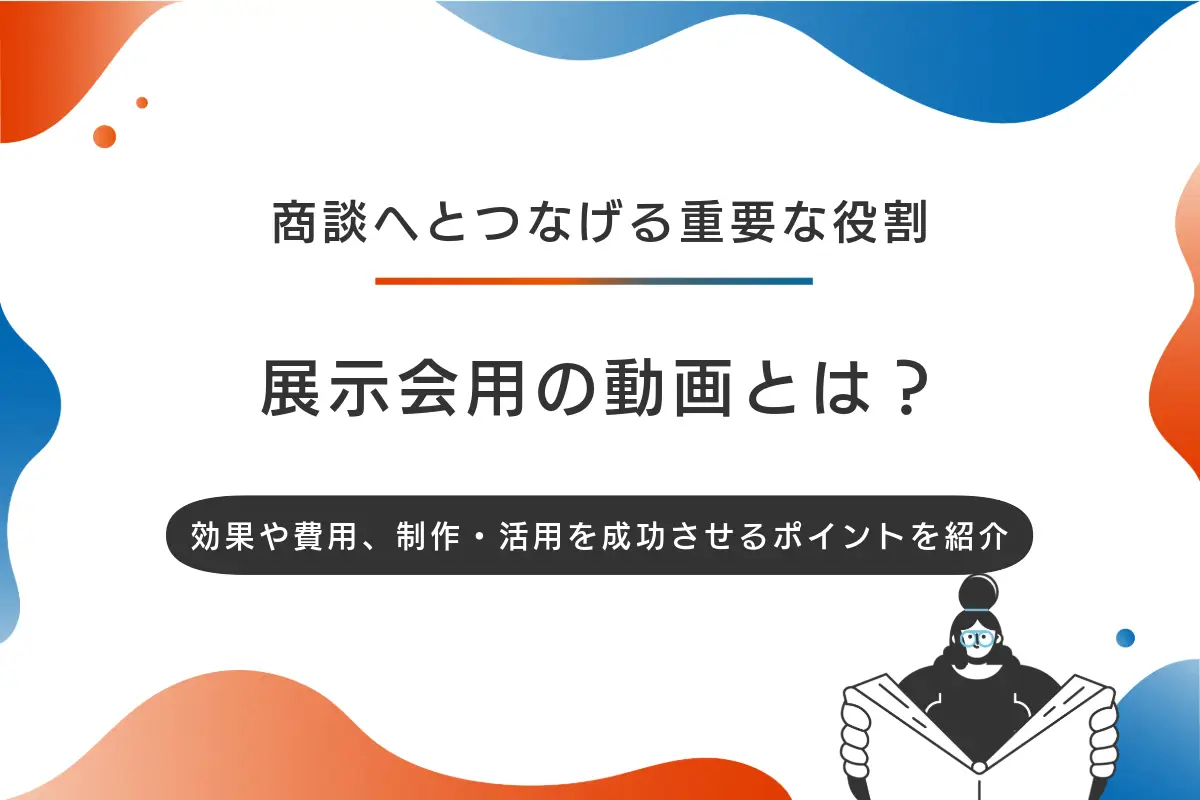
展示会では、限られた時間とスペースの中で、多くの来場者に自社の商品やサービスの魅力を伝えなければなりません。その際に、効果的な情報伝達ツールとして活用されるのが「展示会用動画」です。
視覚と聴覚に訴えかけられる動画は、ブースへの集客力を高め、商談へとつなげる重要な役割を果たします。
この記事では、展示会用動画の種類や活用方法、成功のポイントを解説します。ぜひ、展示会での集客・商談化率を高めるためのヒントにしてみてください。
展示会用動画の種類
一口に展示会用の動画といっても、その種類や内容は以下のようにさまざまです。
商品・サービス紹介動画
ティザー広告動画
テスティモニアル動画
会社紹介動画
プロモーション動画
ここでは、どのような動画が展示会で活用できるのかについて、詳しくみていきましょう。
商品・サービス紹介動画
商品・サービス紹介動画は、商品やサービスの特徴をわかりやすく伝えるための動画です。展示会では、来場者に短時間でメリットや使用方法を理解してもらうことを目的に活用されることが一般的です。
技術的な強みや使用イメージを映像として見せることで、口頭で説明するよりも興味を引きやすくなります。展示会はもちろんのこと、営業活動や新人研修、企業のWebサイト、YouTubeなど幅広いシーンで利用できるので、長期的なメリットが豊富な動画だといえます。
関連記事:サービス紹介動画とは?作り方や成功のポイント・制作の注意点を解説
ティザー広告動画
ティザー広告動画は、視聴者の興味を刺激するために商品やサービスの一部分だけを紹介する動画です。展示会で流すことで、通行している来場者の関心を引いて、ブースへ誘導しやすくなります。
新商品の発表前や新規サービスの告知などに用いられることも多く、展示会以外にも、SNSやWeb広告などで事前プロモーションをしたいときに活用できます。具体的な機能や詳細についてはあえて言及しないので、視聴者の期待感を高め、商談やプレゼンテーションへつなげたいときに効果的です。
テスティモニアル動画
テスティモニアル動画は、「お客様の声」などの顧客や専門家からの推薦コメントを紹介する動画です。第三者の客観的な意見を紹介することで、商品やサービスの信頼性を高める効果があります。
ブースを訪れた来場者に「顧客がどのように評価しているのか」「どのような成功事例があるのか」を伝えれば、購買意欲や商談の成約率を向上させやすくなるでしょう。ただし、テスティモニアル動画単体では何を紹介しているのかがわかりにくいので、商品・サービス紹介動画と組み合わせて活用することがおすすめです。
会社紹介動画
会社紹介動画は、自社の事業内容やサービスを紹介し、企業の信頼性を伝えるための動画です。特に、中小企業やベンチャー企業にとっては、自社の強みや独自性をアピールし、認知度を高める手段として非常に有効です。
来場者に自社のビジョンや価値観を伝え、信頼感の醸成やブランディング力を高める効果があります。再編集することで、展示会だけでなく採用活動や企業のWebサイト、営業活動でも幅広く活用できます。
関連記事:企業紹介動画の作り方を紹介!活用方法や効果、成功のポイント
プロモーション動画
プロモーション動画は、企業全体のブランドメッセージを伝えるための動画です。特定の商品やサービスについて言及するのではなく、企業自体のイメージを向上させる構成になっています。
展示会では、「説明会の前に流して集客する」「プレゼンテーションの冒頭で流して来場者の関心を引く」といった活用が可能です。SNS広告やホームページなどにも流用できるため、ブランド価値を高めるマーケティングツールとして長期的な利用が見込めます。
展示会用の動画を作るメリット・効果
展示会用の動画を作ることには、以下のようなメリット・効果があります。
来場者の注意を引ける
展示会の人員を削減できる
効率よく営業活動ができる
会場にない商材も紹介できる
オンライン展示会にも活用できる
どのような効果があるのか、具体的にみていきましょう。
来場者の注意を引ける
いくつものブースが並んでいる展示会で来場者の目を引くには、興味を抱いてもらうための工夫が必要です。そこで有効なのが、視覚的なインパクトが強く、映像や音声で相手の興味を引きやすい動画の活用です。
短時間で多くの情報を伝えられる動画があれば、ブースの前で来場者に足を止めてもらいやすくなります。さらに、足を止めてじっくり動画を見ている来場者は、自社の商品やサービスに興味を持っている可能性が高いので、確度の高いリードを見極めやすくなる点もメリットです。
展示会の人員を削減できる
展示会では、来場者一人ひとりに丁寧に対応する必要があるので、スタッフを何人も配置しなければいけません。しかし、動画を活用すれば、商品の特長や導入事例、操作方法などの説明を自動化できるため、人的リソースを削減できます。
録画で対応すれば、担当者や講師などが当日不在でも専門的な解説が可能です。展示会運営がスムーズになり、当日参加するスタッフの負担も軽減できるでしょう。
効率よく営業活動ができる
短時間で多くの来場者にアプローチしなければいけない展示会では、営業担当者が何度も同じ説明を繰り返すことになります。このときに動画を活用すれば、営業担当者が説明する手間を最小限に抑えて、短時間で効率的に商品やサービスの魅力を伝えられます。
さらに、一定のクオリティで説明が可能になるので、成果が営業担当者のスキルに依存しにくくなる点もメリットです。
会場にない商材も紹介できる
展示会では、物理的な制約によって、大型の機械や精密機器、危険物などを持ち込むことが難しい場合があります。会場に持ち込めなかった商材も、動画を活用すれば詳しく紹介することが可能です。
例えば、製造工程を紹介する動画や工場を映した映像を用意すれば、実物がなくても来場者にイメージを伝えられます。また、無形商材やデジタルサービスの場合は、画面操作のデモ動画などを流せば、魅力を視覚的に伝えやすくなります。
オンライン展示会にも活用できる
近年は、オンラインで展示会や商談が行われる機会が増えてきました。展示会用に制作した動画は、このようなオンライン展示会やWeb商談でも活用できるため、一度制作すれば長期にわたって役立ってくれます。
オンラインイベントでは、相手に直接商品を手に取ってもらうことができないので、動画を活用した情報提供は特に高い効果を発揮します。
展示会用動画の制作を依頼するときの費用
展示会用の動画を制作するときは、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
ここでは、「新規で動画を制作する場合」と「既存の素材を再編集する場合」の2パターンに分けて費用相場を紹介します。
新規で制作する場合
実写動画:50万~400万円
アニメーション動画:50万~300万円
展示会用動画をゼロから制作する場合、実写動画もしくはアニメーション動画のいずれかを選ぶことになります。
一般的な相場は、実写動画で50万~400万円、アニメーション動画で50万~300万円ほどです。費用は、動画の尺や撮影の規模、キャスティング、CG・アニメーションの有無、編集の工数などによって大きく変動します。
実写動画は、製品やサービスの特徴や使用シーンをリアルに伝えやすく、信頼感を醸成しやすい点がメリットです。一方でアニメーション動画は、抽象的な概念や仕組みをわかりやすく説明できるため、無形商材や技術的なサービスの紹介に適しています。
既存の素材を再編集する場合
すでに保有している動画素材を再編集する場合は、新しく撮影を行う必要がないので、5万~10万円ほどのコストで制作が可能なケースもあります。ただし、カットの変更や字幕・テロップの追加、BGMやナレーションの差し替えなど、編集作業の内容によって費用は変動します。
過去に他の制作会社に作ってもらった動画を再編集するときは、著作権やライセンスに関する確認が必要です。勝手に編集すると権利侵害になる可能性があるため、あらかじめ制作会社との契約内容を確認しておくことが大切です。
展示会用動画の制作を成功させるポイント
展示会用の動画制作を成功させるために意識したいポイントとして、以下のようなものがあります。
映し出す媒体に合わせて制作する
コンパクトに仕上げる
インパクトのある内容にする
字幕やテロップをつける
クリアな音声を使う
各ポイントの詳細を説明します。
映し出す媒体に合わせて制作する
展示会用動画は、プロジェクターやデジタルサイネージ、大型ディスプレイなどで再生されることが多いため、映し出す媒体に合わせて制作することが大切です。
例えば、スマートフォン向けの動画を大画面に表示すると、画質が粗くなって視認性が低下する可能性があります。反対に、大画面向けの高解像度動画をタブレットや小型モニターで再生すると、データ容量が大きすぎて再生できないかもしれません。
事前に使用する機材を確認し、それに適した解像度やフォーマットの動画を制作しましょう。
コンパクトに仕上げる
展示会の来場者は、短い時間でより多くの情報を収集しようと考える傾向にあります。長尺の動画は最後まで視聴してもらえない可能性が高いので、要点を絞って1~2分程度で完結する動画に仕上げましょう。
短時間で伝えたい情報を的確に整理したうえで、一瞬で通りがかった視聴者の関心を引きつける構成にすることが大切です。
インパクトのある内容にする
展示会場では、多くのブースが動画を活用しているため、単に動画を流すだけでは十分な効果を得ることはできません。成果につなげるには、他社と差別化できる動画の制作が求められます。
単に商材の特徴を説明するだけでなく、「アニメーションやCGを取り入れる」「ユニークな演出を施す」など、興味を引くための工夫が必要です。単調な動画は飽きられやすいので、メリハリやオリジナリティを意識してみましょう。
字幕やテロップをつける
多くの来場者でにぎわっている会場では、音声による説明だけでは内容が伝わりにくい場合があります。騒がしい状況でも対応できるよう、動画には字幕やテロップをつけて理解を促進しましょう。
特に、重要なキーワードや情報は目立つように表記して、視聴者が一目で理解できるようにしておくと親切です。海外の方もターゲットにしている企業は、日本語と英語の字幕を併記してもよいでしょう。
クリアな音声を使う
動画を制作するときは、音質にもこだわりましょう。音質の悪いナレーションや雑音が多い音源を使用すると、周囲の騒音と混ざって聞き取りにくくなり、来場者にとってストレスの原因になることがあるためです。
BGMやナレーション、効果音(SE)は、できるだけクリアで聞き取りやすいものを選びましょう。
展示会用動画を活用するときのコツ
展示会で動画を最大限に活用するために、VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)の考え方を取り入れることがおすすめです。
VMDとは、視覚的な演出を通じて商品やブランドの魅力を伝える手法です。展示会では、VP(ビジュアル・プレゼンテーション)、IP(アイテム・プレゼンテーション)、PP(ポイント・オブ・セールス・プレゼンテーション)という3つの要素を意識すると、より動画の効果を引き出しやすくなります。
項目 | 概要 | 具体例 |
VP(ビジュアル・プレゼンテーション) | ブース全体の第一印象を決定づけるもの |
|
IP(アイテム・プレゼンテーション) | 個々の商品やサービスを魅力的に見せる手法 |
|
PP(ポイント・オブ・セールス・プレゼンテーション) | 興味を抱いたユーザーを次のアクションにつなげる工夫 |
|
また、動画の再生場所やタイミングを工夫することも大切です。
ブースの入口ではインパクトの強い短めの動画を流し、ブース内部では詳細な説明を含む長めの動画を再生すると、来場者の関心度に応じた情報提供が可能になります。
展示会用の動画制作ならコンマルクへご相談ください!
展示会用の動画は、来場者の興味を引いて集客したり短時間で商材について伝えられたりと、メリットの多いツールです。
ただし、単に会場で動画を流すだけでは、成果につなげることはできません。効果的に動画を活用するには、ターゲットに響く映像の制作や商談につなげる導線設計など、さまざまなポイントを押さえておく必要があります。
展示会用動画の制作なら、ぜひ株式会社GIGのメディア事業部が運営するサービス「コンマルク」までご相談ください。
コンマルクは、数百万PV〜数億PVのメディア構築実績を持つ専門家集団であるGIGのメディア編集部が、貴社の事業成長に必要不可欠なメディア運営や動画制作を強力にバックアップするサービスです。
企画から編集まで一気通貫でサポートし、ブランドやサービスのコンセプトと一貫した動画の制作が可能です。さらに、動画を活用したマーケティング施策の戦略立案や実行支援にも対応。「何か困ったとき」のパートナーとして最後まで伴走いたします。
また、各種Webマーケティング施策やWebコンサルティングの実施にも対応しています。集客にお悩みの方は、ぜひお気軽にコンマルクにご相談ください。
コンマルクの映像制作・動画制作サービスについてはこちらで紹介しています。
お問い合わせはこちらから

コンマルクは、コンテンツ制作、インタビュー取材、マーケティング設計、メディア運営、サイト分析改善など、上流から下流までトータルで伴走するコンテンツマーケティング総合パートナーです。コンテンツ制作やWebマーケティング、ブランディング、広報、動画領域に詳しいメンバーが情報発信をしています。